ぜんぶふぇありー
1/1FAIRY!
words by アラスカの荒らし屋
「かぼちゃパイ食べる?」
軽率なことを言ったのかも知れない。どうしたものだろうかという戸惑いを覚えながら、ラスは横目で、傍らの少女を観察していた。緩くウェーブのかかった金色の髪に鳶色の瞳、その瞳に大粒の涙を浮かべながら、大きすぎる椅子に所在無げに腰掛けて、フォークでかぼちゃパイをつっついている。綺麗な娘だな、と素直に思う。しかし先刻の言動といい、あの服といい…あの服、寒くないのかな?寝間着なのかな?ネグリジェとか…いや割烹着と言った方が適当なのか……
その時、背中に促すような視線を感じて、ラスは茫漠とした思考を中断した。「解ってるって」と台所の母を一瞥してから、目の前の課題に意識を集中することにして、少女とまっすぐ向かい合うように椅子を動かして座り直し、切りたくもない口火を切る。
「さて、始めようか迷子ちゃん」
少女はかぼちゃパイをつっつくのをやめて、まだ涙が溜まっている瞳で、上目使いにラスを見上げた。その瞳に不安と戸惑いを見出して、「何で僕なの」という思いがラスの頭をかすめたが、忘れることにして言葉を続ける。
「え、と、急いでるんだったよね」
やばい。少女の瞳に再び大粒の涙が満ちてくるのを見て、慌てて言い募る。
「あ、確か丘を探してるんだっけ。でも、丘っていってもよく解らないから、もう少し詳しく説明してもらえられば嬉しいな。そうすればもしかしたら役に立てるかもしれない。それと、その、名前を教えてくれるかな」
「名前はフェリサ…です」
「フェリサちゃんね。そう、素敵な名前だ、うん」
取り敢えずの危機を避けるために、我ながらかなり調子のいいことを言っていると思う。ラスがそんなことを考えている間に、少女、フェリサは、どうやら泣き出すのを堪えたようで、たどたどしく説明を始める。
「丘、っていうのは…ええと、丘です。…じゃなくて小高くなった…」
「つまり丘ってこと?」
「あの、そうじゃなくて、あ、そうなんですけど、その、丘の下に私が住んでいるところがあって、それが丘なんですけど、あの…」
これは骨が折れるぞ。顔を真っ赤にして必死に説明しているフェリサを見ながら、ラスはそっとため息をついた。
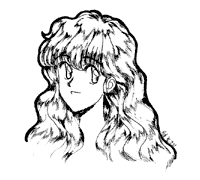
三十分後、ラスは自分の予測が甘かったことを思い知っていた。
「つまりこういうことだね。フェリサちゃんは妖精で、普段は妖精の国に住んでいる。で、ハロウィンには妖精の国と人間の世界がつながるから、人間の世界に遊びにきた。でも、迷ってしまって妖精の国に帰れなくなってしまった。その妖精の国と人間の世界とがつながっている場所が丘で、しかもハロウィンが終わると妖精の国に帰れなくなってしまう。あと2時間ちょっとかな」
「はい」
「でも、さっきも言ったけど、この辺りにフェリサちゃんの言ってたような丘ってのは知らないけどな。あ、泣かないでね」
フェリサは小さく頷いた。どうやらフェリサは、夢中で遊んでいるうちに完全に迷ってしまったらしく、丘の位置もまるで見当がつなかいようだった。どうしようもないな、というのがラスの率直な感想である。
「私、帰れなくなっちゃったんですね」
フェリサが涙を堪えながらぽつりと言う。かわいそうにと思っても、ラスにはどうしようもなかったが、応急処置をとることはできた。
「ええと、あの、もしよかったら取りあえず今日は、夜も遅いし、この家に泊まったらどうだろう、以後のことは明日考えるってことで、ね」
一息で言い切ってから、「でも妖精って眠るのかな?」などと、ラスが皮肉っぽく考えていると、フェリサがぺこりと頭を下げた。
「すいません」
「こちらこそ、役に立てないでご免」
その場しのぎの解決に、ラスは心底ほっとした。後ろを振り返り、一部始終を窺っていたであろう母に声をかける。
「そういうことになったから、部屋を用意してよ」
「はいはい」
返事をして二階に上っていく母を目で追ってから、ラスはひとつ伸びをして椅子から立ち上がると、自分も二階に向かおうとした。
「あの」
フェリサの遠慮がちな声に振り返る。
「ん?」
「あの…、名前を教えて貰えませんか」
そう言ったフェリサの瞳に、拒絶されたらどうしようかという恐怖をみとめて、信じてみるのも悪くないのかな、とラスは漠然と思った。
★
コン、コン。
ラスは控え目なノックの音で目を覚ました。昨日は夜遅くまで新人賞に応募する小説の原稿を書いていたのでもっと寝ていたいが、母は意地でも朝食を食べさせようとするだろう。
「起きてるよ、フェリサ。すぐ行く」
寝間着を脱いで、普段着に着替える。寝癖はひどくないかな、と鏡を見た自分に、ラスは苦笑してしまった。家の中でそんなことを気にするなんて、変われば変わるものだと思いながら、そんなに悪い気分ではない。寝癖を手で抑えながら一階に降りていくと、パンとアップルパイの臭いがしていた。
「おはようございます」
「おはよう」
元気のよいフェリサに答えながら、なんで彼女はあんなにいつも楽しそうなんだろう、と思う。特に朝は、はしゃいでいるというのが適当なくらい元気がいい。
ハロウィンから三日、フェリサはファーガソン家にもうすっかり馴染んでいた。話によると次に妖精の国と人間の世界がつながるのはミドサマー・イヴだそうで、それまでは妖精の国に帰れないそうだ。暫く帰れないという話を聞いて、じゃあ帰れるようになるまでこの家にいればいいじゃない、と母が言った時に、フェリサは泣きながら頭を何回も下げていたものだ。今では母、それに父も、人見知りせず屈託の無いフェリサを非常に気に入っている。おおらかというかいい加減な両親に、ラスは初めて感謝した。彼女が妖精だっていう話は当然伏せてある。頭がおかしいと思われるのがオチだし、折角まとまりかけている話をややこしくするだけだ。とは言うものの、ラスもそんな話はまったく信じられないのである。
「ぼーっとしてないで、早く席につきなさい」
母に言われて我に帰り、テーブルにつくと、フェリサがパンとミルク、そして焼き立てのアップルパイを食卓に並べて、ラスの隣の椅子に座る。
「本当にりんごが好きなんだね」
ラスはフェリサに声をかけた。実際フェリサはりんごが好きで、毎日のように彼女のりんご料理が食卓に並ぶようになった。
「はい。あちらではほとんどりんごと豚肉でしたから」
「あら珍しいのね」
これは母だ。
「でも、りんごの木は枯れませんし、豚さんも次の日には」
「ごほん」
わざとらしい咳払いをして、ラスがフェリサを目で注意すると、フェリサは慌てて口を押さえ、ラスに向かって「失敗、失敗」という風に舌をだした。そのやりとりを不思議そうに眺めながらも深くは追求しようとしない父と母を、ラスは本当に嬉しく思った。
★
日曜日、ラスは遅い朝食を終えると、二階の自分の部屋で外出の支度をしていた。
「ラス、早くしなさい。フェリサちゃん待ってるわよ」
母が一階から大きな声で呼んだ。
「わかってるって」
ラスは同じような大きな声で生返事をしてから、気乗りのしない様子で外出の支度を続けた。昨日、新人賞に応募する小説の原稿を書き上げ、郵送も済ませて、解放された気分で二、三日は安穏と惰眠をむさぼる予定だったのに、どうしてこんなことになったんだろうか。母はどうやら、小説家の卵には休息の必要を認めてくれないらしい。遊ぶったって、どこで何をやれっていうんだ……。いけない、どうも負の方向にしか考えられないのは、やっぱり疲れているんだろうか。可愛い女の子とのデートには間違いないんだから…そういえばフェリサって何歳なんだろう?初めて会った時には少女という印象だったが、この頃は年齢不詳という感じだ…
やめた。下らない思考に終止符を打ったラスは、その勢いで外出の支度も切り上げることにして、一階に降りていった。
「随分時間をかけた結果がそれ?」
「何を期待していたんだよ、不肖の息子にさ」
母の皮肉に苦笑とともに答ながら、ラスはフェリサに目をやった。フェリサは山吹色のチュニック・セーターに、薄い茶色のプロヴァンシャル・スカート、肩にはストールを掛けている。今までは有り合わせのものを、例えばラスのYシャツなどを着用していたのに、なるほど、昨日母と二人で外出していたのはそういう訳だったのかとラスは納得して、ストールのフリンジを不思議そうに弄ぶのに夢中なフェリサに声をかけた。
「おまたせ、フェリサ。行こうか」
フェリサはフリンジから目を上げてラスを見ると、花が咲くように笑った。
「とーっても楽しみにしてたんです。今日はよろしくお願いします、ラスティさん」
とーっても、という両腕を大きく広げる動作を見ながら、ラスは「今にも踊り出しそうだな」と思った。本当に楽しそうだ………
「あの、もしかしたら迷惑でしたか?」
フェリサの申し訳なさそうな声でラスは我にかえった。しまった、見とれてしまっていた。それがどうやら、フェリサには乗り気でないように見えたらしい。
「いや、そんなことはないよ。あの、それと、フェリサ、可愛いね」
唐突に言ってしまった。言った直後にしまったと思ったが、後の祭りだ。母の方を極力気にしないようにしながら慌てて言い足す。
「その服、よく似合ってる。さ、行こうか、フェリサ」
ラスはそのままくるりと後ろを向くと、玄関に向かって歩き出した。母の表情を想像すると、自分の軽率さが嫌になるが、ちらりと目に入ったフェリサの嬉しそうな笑顔で帳消しにすることにして、自分を納得させる。フェリサが母に一礼してから後ろをついてくるのを気配で確認すると、ラスは言った。
「それと、ラスティさんなんてやめてくれ。ラスでいいよ」

「ラス、こっちこっち」
氷の上を滑りながら、フェリサがラスに手を振った。スケートを初めて見た、と言っていた割にはすぐに順応して、今では自由に滑っている。
ラスは、何とか言い訳を考えて、リンクの外からフェリサの相手をするという立場を確保した。
おざなりに手を振り返しながら、どうやらフェリサが楽しんでいるようで、取りあえずはよかったな、とラスは思った。それにしても、ここに来るまでもフェリサは目に入るものにいちいち興味を示しているように見えたし、スケートも滑稽なほど楽しんでいる。もっとも、滑れないラスにはスケートの面白さなんて解らないことではあるが…。妖精だ、ってのは論外としても、どこかしら普通でないことは間違いない。別に頭がおかしいってんでもないようだし…
「どうしたの?ラス」
突然、目の前にフェリサの顔があった。また呆けていたようで、悪い癖だ、と思いながらラスは答える。
「あ、ご免、何でもないよ、時々こうなんだ。それより、どうしたの?もう滑らないの」
「ちょっと疲れちゃった」
そう言ってフェリサは、スケート靴でヨロヨロとベンチまで歩いていって倒れ込むように座った。ラスもその隣に座る。
「楽しかった。スケートってとっても楽しいわ。あんなに大きな氷なんて見たこと無いからびっくりしたけど、上を滑れるものなのね、氷って。くるくる回ったり、ぴょんって跳んだり色々できるようになったのよ、ね、ラス、見えてた?」
こちらをまっすぐに見据えて捲し立てるフェリサに、ラスは圧倒された。
「た、楽しんでるみたいだね、よかった」
「でも、何でラスは滑らないの?そんなに子供っぽいかな?」
話の雲行きが怪しくなってきた。ラスはささやかな名誉と自尊心のために、話題を転換する必要を感じた。
「あ、でも、あんなに大きな氷ってどういうこと?スケートが始めてってのは、まあ解るんだけど」
「妖精の国、常若の国はいつでも夏なんです。氷も小さいものしかありませんし」
あ、しまった。こちらも鬼門だったか、とラスは思った。さすがに妖精云々の話にはついていけない。そんな気持ちが表情に出てしまったのだろうか。
「でも、信じていらっしゃらないんでしょう?私の話」
フェリサが淋しそうに言う。
「無理もありませんよね、妖精だなんて」
フェリサはすっかり元気を失って続ける。目をそらしてあらぬ方を見つめるフェリサの瞳に、疑いようのない悲しみを見て、ラスは心底後悔した。
「いや、信じないってんじゃないんだけどね。その、何て言うか、努力はしているんだけど、その、つまり……」
「いいんです。すいません、変なこと言って」
フェリサは再びこちらを向いて微笑みながら言った。しかしラスには、その笑顔は普段のフェリサのものではなく、その瞳からは悲しみが消えていないのが、はっきりと解った。
「あの、そろそろ帰りましょうか。寒くなってきましたし」
「あ、ああ、そうだね。それじゃスケート靴を返さないと。フェリサの靴を取ってくるよ、待っててね」
不必要に明るく言うと、ラスは立ち上がり、フェリサの靴を取りに行こうとした。その時、
「今日はありがとうございました。とっても楽しかったです」
フェリサが背中から明るさを装って言った。ラスは自分が嫌になった。
★
―落選―
新人賞の結果が出た。初めてのことではないが、やはりこたえる。もうすぐクリスマスだというのに、これで数日は暗い気分で過ごさなければならない。今日はさすがに母も何も言わないだろうから、一日中自分の部屋に閉じこもってふて寝でもしていよう、ラスはそう決心して、ベッドに体を投げ出したが、眠くもないのにそう簡単には眠れない。行き場のない視線を窓の外に向けると、四日前から降り続けている雪だけが見えた。そういえば、フェリサが三日前から大きな雪だるまの制作に着手していたっけ。今では玄関の横に八割方完成した雪だるまがデンと控えているはずだ。
フェリサ…。彼女はあの日以降、まったく普通に戻っていた。ラスも気を付けていたし、フェリサがその類の話題を軽率に皆の前で、ラスの前でも、口にすることも無くなった。だからあのような状況はあれから一度もなかったが、ラスは今でもあの日の気分を引きずっていた。真剣に自分が嫌になったのは初めての経験だった。結構なロマンチストのつもりだったんだがなあ…。蓋を開けて見ればこんなものだった訳だ……話の語り手としても失格だな、こんな男のヘボ小説が面白いわけがない………
コン、コン。
際限なく深く沈んでいきそうなラスを、控えめなノックの音が現実に引き戻した。母か?いや、このノックはフェリサだな…ラスは返事をするのを躊躇ったが、結局返事をすることにした。
「何?」
「あの、雪だるまが完成したんで…」
慰めに来てくれたのか。ラスはこの一月あまりでフェリサが優しい娘だということは十分に解っていたが、その優しさが今の自分に有り難いものであるとはラスには思えなかった。それでも扉を開けると、そこには心配を隠せないでいるフェリサがいた。
「雪だるまが…できたんですけど」
「おめでとう。是非拝見したいものだ」
ラスは作り笑いでそう言うと、先に立って階段を下りていった。
玄関の横には見事な雪だるまが鎮座ましましていた。その目が、鳥の足跡のような、「きゅーっ」といった感じになっているのを見て、何か妙にフェリサらしいなと思い、ラスは思わず苦笑してしまった。
「凄いじゃない。立派なもんだ」
努めて明るくラスが言うと、フェリサはラスのすぐ横にきて、真剣に説明を始めた。
「でも、結構小心者なのよ。あんまり雪がいっぱい降るから、驚いてるの。ほら、目もそんな感じだし、両手も上に挙げてるでしょ。うひゃーって」
「雪だるまなのに雪に驚いてるの?」
「そう。ラスだって肉がいっぱい降ってきたら驚くでしょう?」
「それは驚くけど、そういう問題かなあ?」
「そういう問題よ、多分」
他愛もないことを喋っているなあ、と思いながらも、ラスは笑った。フェリサも笑っていた。笑いながらラスはフェリサに感謝した。
「フェリサ」
ラスは笑いをおさめると、真顔で言った。
「ありがとう。気を使わせちゃって悪いね。もう大丈夫だから、心配しないで」
ラスはこの機会に、心に引っかかっているものも一気に清算することにした。もしかしたら触れない方がいいのかもしれない、そう思ったが、謝らずにいるのはやはり嫌だった。
「それと、この間のスケートの時、ごめんね」
フェリサはラスの目をじっと見つめた。唐突に、フェリサと自分との距離が非常に短いことに、ラスは気がついた。
「いいんです、本当に。それよりも私、私のせいで、その、お仕事に差し支えたのかと思って、それだけが心配で、もしそうだったらどうしよかと…」
ラスは、とつとつと話すフェリサの瞳にあるのが、悲しみよりもむしろ、あのハロウィンの夜の恐怖であることに気がついた。ラスの中に、たまらなくフェリサを愛おしく思う気持ちがわき上がってきた。抱きしめたい、そう思ったが、生来の臆病が邪魔をする。いけ、抱きしめろ、ラスティ=ファーガソン!
「あの、どうしました?」
フェリサがラスの様子のおかしいのに気がついて声をかけるが、もはやラスには聞こえなかった。
「フェリサ」
ラスは意を決した。不自然なくらい緊張した真顔で、じりっとフェリサとの距離をつめると、フェリサの肩に手をかける。フェリサが慌てる。
「え、ラス?」
いくぞ!ラスがフェリサを抱きしめた時―
フェリサは消えた。
消えた?ラスは冷静に判断ができなかった。一体何が起こったんだ?と、上からフェリサの声がした。
「ごめんなさい、ラス。だって何か怖かったんだもの、ラスったら」
ラスが声のした方を見上げると、そこにはフェリサが、空中にふわふわと浮いていた。
「ね、許して、ラス」
ラスは茫然自失の体で、何やら喋っているフェリサを見上げていた。
「ラス、怒ってるの?」
反応がない。
「ねえ、ラス」
また、反応がない。
「ラス?」
突然、ラスは大声をあげた。
「やったー、凄いよ、凄いよフェリサ!」
今度はフェリサが呆気にとられる番だった。ラスは空中にいるフェリサの手をとると地上に下ろし、笑いながら大声でフェリサの知らない歌を歌い、無理矢理一緒にダンスを踊り始めた。すぐにフェリサは自分から踊るようになり、雪の中で、二人のダンスは暫く続いた。
踊りながらフェリサは思った。
「最初からこうすればよかったのね…」
★
翌年のミドサマー・イヴにラスティ=ファーガソンとフェリサは結婚した。
[ back to index ]
[$Id: allfairy.html,v 1.2 2001/11/10 18:08:47 lapis Exp $]
|